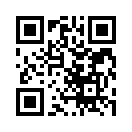2011年07月15日
世界の捉えなおし…哲学
最近、『哲学的な何か、あと科学とか』というサイトにはまっていた。
一般的な哲学のイメージがどういうものか知らないが、このサイトは、「哲学って面白いものなんだ」ということを十分に伝えてくれた。
映画『マトリックス』は哲学的な要素を設定に持ってきてはいるものの、結局ハリウッドの映画の枠を超えることはできなかった。
それは本当に哲学に興味を持っている人には十分ではないと思う。まぁ、マトリックスはそういう人のために作られたわけではないから、仕方ないんだけれど。
『ソフィーの世界 - 哲学者からの不思議な手紙』(ヨースタイン・ゴルデル 1995 日本放送協会)は、流行った頃に読んでみたが、哲学(あるいは哲学的問題というべきか?)の紹介というよりは、「誰それがどう考えた」という哲学者の羅列である、西洋哲学史の域を出ていないと感じた。
その点で『翔太と猫のインサイトの夏休み』(永井均 1995 ナカニシヤ出版)は、「誰それがどう考えた」という哲学者の羅列ではなく、物語仕立てで哲学の諸問題を紹介しているのでわかりやすかった。
この本には、15歳を過ぎたら本当の哲学はできなくなる、というような内容(うろ覚え)のことが書いてある。これは実際そうなのかもしれない。哲学で考えられていることはごく当たり前のことだからだ。「自分って何?」とか、考えても結局ごく当たり前の結論にしかならないことが多い。その思考過程において、映画『マトリックス』の設定に用いられたような事も考えるため、哲学の話題の中には不思議だったり、突飛だと感じたりするものもあるのだ。
ある当然の事柄を一生懸命考えて、考え抜いても現実的に仕方がない、ということが大人になるに従って経験的にわかってくる。要するに、「今が夢でなくて現実である理由」だとか、「なぜ赤は赤に見えるのか」、「自分が見ていない時でも友人や家族は存在しているのか」なんて考えたところで、現実的に何も変わらないし、よしんば「自分が見ていない時でも友人や家族は存在しているのか」ということが事実だとしても、確かめようのないことだから考えても仕方がない、ということが大人はわかってしまうから、世の中がわかり始める15歳あたりから哲学ができなくなるのだろう。
けれど、当たり前の事柄A(便宜上Aとする)について何の思考もなくAと認識するのと、A について考え抜いたうえでAと認識するのでは、世界の捉え方が全く変わってくる。つまり、哲学をするというのは世の中を捉えなおす、ということなんだろう。
これはかなり重要なことだと思う。
考えてみれば、いろいろな言説について日本社会は哲学をしているだろうか。例えば、このブログでも散々問題にしているが、「日本」「日本人」と一口にいった場合何を指して言っているのか、どれだけの人が思考しているだろうか。考えても仕方ない、考えるまでもなく自明のことだとして切り捨てた思考の中に、どれだけの「真理」が隠されているのか、そこはきちんと考え直すべきだと思う。
『哲学的な何か、あと科学とか』は書籍として2006年に出版されている。『翔太と猫の~』とあわせて読めば、さらに哲学に対しての理解が深まると思う。
哲学の本に自然科学の分野が顔を出すのは一瞬奇異な感じもするが、量子力学の話を読めば納得できる。光が粒子か波かの議論から始まった、電子の二重スリット実験による結果は、この世の中の物質が全て、(矛盾した二者が同時に存在するという意味で)言語道断で、でたらめなものから構成されていることを実証してしまった。
そういうわけで、量子力学は哲学的な問題をそもそもはらんでいるのだ。
んでも、矛盾した二者が同時に存在(すべてものを貫く矛と、すべてのものを防ぐ盾が同時に存在する状況を考えてみてください。電子は実験で、その状況に値する振る舞いをしてしまいました。)するものでできている世界というのは、結構面白いんじゃないかなと思う。
一般的な哲学のイメージがどういうものか知らないが、このサイトは、「哲学って面白いものなんだ」ということを十分に伝えてくれた。
映画『マトリックス』は哲学的な要素を設定に持ってきてはいるものの、結局ハリウッドの映画の枠を超えることはできなかった。
それは本当に哲学に興味を持っている人には十分ではないと思う。まぁ、マトリックスはそういう人のために作られたわけではないから、仕方ないんだけれど。
『ソフィーの世界 - 哲学者からの不思議な手紙』(ヨースタイン・ゴルデル 1995 日本放送協会)は、流行った頃に読んでみたが、哲学(あるいは哲学的問題というべきか?)の紹介というよりは、「誰それがどう考えた」という哲学者の羅列である、西洋哲学史の域を出ていないと感じた。
その点で『翔太と猫のインサイトの夏休み』(永井均 1995 ナカニシヤ出版)は、「誰それがどう考えた」という哲学者の羅列ではなく、物語仕立てで哲学の諸問題を紹介しているのでわかりやすかった。
この本には、15歳を過ぎたら本当の哲学はできなくなる、というような内容(うろ覚え)のことが書いてある。これは実際そうなのかもしれない。哲学で考えられていることはごく当たり前のことだからだ。「自分って何?」とか、考えても結局ごく当たり前の結論にしかならないことが多い。その思考過程において、映画『マトリックス』の設定に用いられたような事も考えるため、哲学の話題の中には不思議だったり、突飛だと感じたりするものもあるのだ。
ある当然の事柄を一生懸命考えて、考え抜いても現実的に仕方がない、ということが大人になるに従って経験的にわかってくる。要するに、「今が夢でなくて現実である理由」だとか、「なぜ赤は赤に見えるのか」、「自分が見ていない時でも友人や家族は存在しているのか」なんて考えたところで、現実的に何も変わらないし、よしんば「自分が見ていない時でも友人や家族は存在しているのか」ということが事実だとしても、確かめようのないことだから考えても仕方がない、ということが大人はわかってしまうから、世の中がわかり始める15歳あたりから哲学ができなくなるのだろう。
けれど、当たり前の事柄A(便宜上Aとする)について何の思考もなくAと認識するのと、A について考え抜いたうえでAと認識するのでは、世界の捉え方が全く変わってくる。つまり、哲学をするというのは世の中を捉えなおす、ということなんだろう。
これはかなり重要なことだと思う。
考えてみれば、いろいろな言説について日本社会は哲学をしているだろうか。例えば、このブログでも散々問題にしているが、「日本」「日本人」と一口にいった場合何を指して言っているのか、どれだけの人が思考しているだろうか。考えても仕方ない、考えるまでもなく自明のことだとして切り捨てた思考の中に、どれだけの「真理」が隠されているのか、そこはきちんと考え直すべきだと思う。
『哲学的な何か、あと科学とか』は書籍として2006年に出版されている。『翔太と猫の~』とあわせて読めば、さらに哲学に対しての理解が深まると思う。
哲学の本に自然科学の分野が顔を出すのは一瞬奇異な感じもするが、量子力学の話を読めば納得できる。光が粒子か波かの議論から始まった、電子の二重スリット実験による結果は、この世の中の物質が全て、(矛盾した二者が同時に存在するという意味で)言語道断で、でたらめなものから構成されていることを実証してしまった。
そういうわけで、量子力学は哲学的な問題をそもそもはらんでいるのだ。
んでも、矛盾した二者が同時に存在(すべてものを貫く矛と、すべてのものを防ぐ盾が同時に存在する状況を考えてみてください。電子は実験で、その状況に値する振る舞いをしてしまいました。)するものでできている世界というのは、結構面白いんじゃないかなと思う。
Posted by はぬる at 15:12│Comments(0)
│雑感・いろいろ