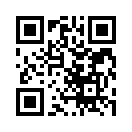2013年07月08日
水滸伝の前史
ある方から、水滸伝に関して非常に有用な情報をいただいた。
なんと、水滸伝の最終成立以前の明代に描かれた、明代の演劇「水滸伝」が出版されるというのだ。
どのような内容になるかはわからないけれど、大宋宣和遺事とか水滸戯とかで語られた豪傑たちの話が読める可能性が高い。
その中には、水滸伝本伝から抜け落ちた話もある。そんな話をまとめて出版するのだろう。
楽しみである。キリッとした李逵とか、だらしない燕青なんかが、なんであんな人物像に変わったかもわかるかも知れない。そこには中国の人々の想いがはっきり現れてくる。
どうやら、この人が翻訳するらしい。
『月刊水滸伝 Webマガジン 2013年5月1日 中国大衆文化のスペシャリスト・岡崎由美教授が「水滸伝」の魅力を分析』
http://suikoden108.com/webmag/6/
ぜひ、駒田信二氏のような名訳を望みたい。
叢雲乃飜さん、貴重な情報をありがとうございます。
m(_ _)m
ところで…
この「月刊水滸伝」というサイト。
オレはあんまり評価していない。
あまりにも水滸伝の初歩者におもねり過ぎている感じがして、逆にしっかり抑えてほしいところがなおざりになっている。
確かに、間口を広げるという点で大きな役割を果たしているのは認めるが(その意味では北方『水滸伝』も同様に間口を広げただろう)、結局そこから広がらない。むしろ、日本人に合わせた水滸伝しか見えないようになっている。
たとえばBooksのページを見ても、完訳の紹介は吉川幸次郎・清水茂両氏によるものしかない。水滸伝を知らせるのであれば、吉川幸次郎氏・清水茂氏のものに合わせて、駒田信二氏の120回本の紹介もあってしかるべきなのにそれがない。
日本人の小説『水滸伝』が大半を占める。
また、上記で紹介したページに
>「三国志演義」「西遊記」とともに中国3大名著のひとつ
などと書いてあるが、「中国3大名著」というくくりはない。
四大奇書なら「三国志演義」「水滸伝」「西遊記」「金瓶梅」、四大名著なら「三国志演義」「水滸伝」「西遊記」「紅楼夢」なのだ。なぜ「金瓶梅」「紅楼夢」をわざわざはずす必要があるのか。(「金瓶梅」はトリビアの中で紹介しているのにもかかわらず!!)
水滸伝を広めたいのであれば、「三国志(三国志演義ではない)」にだけ異常に人気が集まり、「西遊記」「水滸伝」はタイトルだけ、「金瓶梅」「紅楼夢」は名前すら知られていないという日本の状況を問題視すべきだ。
まぁ、「何を細かいことをぶつぶつと…」と思うかもしれない。
けれど、水滸伝を広めたいのなら、岩波少年文庫の『水滸伝』(松枝茂夫訳)のような仕事をこそ、ほめるべきではないだろうか。
それができていないので、オレはあんまり評価していないのだ。
なんと、水滸伝の最終成立以前の明代に描かれた、明代の演劇「水滸伝」が出版されるというのだ。
どのような内容になるかはわからないけれど、大宋宣和遺事とか水滸戯とかで語られた豪傑たちの話が読める可能性が高い。
その中には、水滸伝本伝から抜け落ちた話もある。そんな話をまとめて出版するのだろう。
楽しみである。キリッとした李逵とか、だらしない燕青なんかが、なんであんな人物像に変わったかもわかるかも知れない。そこには中国の人々の想いがはっきり現れてくる。
どうやら、この人が翻訳するらしい。
『月刊水滸伝 Webマガジン 2013年5月1日 中国大衆文化のスペシャリスト・岡崎由美教授が「水滸伝」の魅力を分析』
http://suikoden108.com/webmag/6/
ぜひ、駒田信二氏のような名訳を望みたい。
叢雲乃飜さん、貴重な情報をありがとうございます。
m(_ _)m
ところで…
この「月刊水滸伝」というサイト。
オレはあんまり評価していない。
あまりにも水滸伝の初歩者におもねり過ぎている感じがして、逆にしっかり抑えてほしいところがなおざりになっている。
確かに、間口を広げるという点で大きな役割を果たしているのは認めるが(その意味では北方『水滸伝』も同様に間口を広げただろう)、結局そこから広がらない。むしろ、日本人に合わせた水滸伝しか見えないようになっている。
たとえばBooksのページを見ても、完訳の紹介は吉川幸次郎・清水茂両氏によるものしかない。水滸伝を知らせるのであれば、吉川幸次郎氏・清水茂氏のものに合わせて、駒田信二氏の120回本の紹介もあってしかるべきなのにそれがない。
日本人の小説『水滸伝』が大半を占める。
また、上記で紹介したページに
>「三国志演義」「西遊記」とともに中国3大名著のひとつ
などと書いてあるが、「中国3大名著」というくくりはない。
四大奇書なら「三国志演義」「水滸伝」「西遊記」「金瓶梅」、四大名著なら「三国志演義」「水滸伝」「西遊記」「紅楼夢」なのだ。なぜ「金瓶梅」「紅楼夢」をわざわざはずす必要があるのか。(「金瓶梅」はトリビアの中で紹介しているのにもかかわらず!!)
水滸伝を広めたいのであれば、「三国志(三国志演義ではない)」にだけ異常に人気が集まり、「西遊記」「水滸伝」はタイトルだけ、「金瓶梅」「紅楼夢」は名前すら知られていないという日本の状況を問題視すべきだ。
まぁ、「何を細かいことをぶつぶつと…」と思うかもしれない。
けれど、水滸伝を広めたいのなら、岩波少年文庫の『水滸伝』(松枝茂夫訳)のような仕事をこそ、ほめるべきではないだろうか。
それができていないので、オレはあんまり評価していないのだ。
Posted by はぬる at 21:34│Comments(0)
│雑感・いろいろ